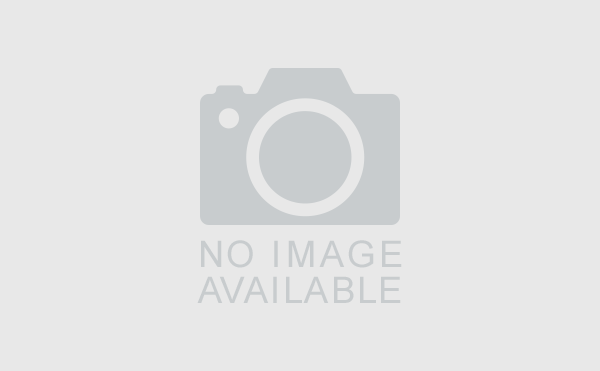【防災シリーズ⑥】災害時の情報収集と電源確保!多機能防災ラジオ
こんにちは、防災Blogです。南海トラフ地震や大規模災害に備える防災シリーズ、今回は「多機能防災ラジオ」について詳しく解説します。

前回の「防災トイレ・簡易トイレ」に続き、今回は災害時に重要となる「情報収集」と「電源確保」の両方を担う防災ラジオを解説します。
東日本大震災では停電によりテレビやインターネットが使えず、多くの方がラジオから情報を得ていました。また、南海トラフ地震では広域かつ長期の停電が予測されており、スマートフォンの充電手段の確保も大きな課題です。
そこで今回は、災害時の必需品である多機能防災ラジオについて、手回し充電・ソーラー充電機能や、スマホ充電機能を中心に解説します。
目次
■災害時の情報収集と電源確保の重要性
大規模災害時の情報入手手段
災害時、特に大規模な地震発生時には以下のような状況が予想されます:
- 停電によりテレビやインターネットが使用不可
- 携帯電話基地局の損傷によるスマホ通信障害
- バッテリー切れによるスマホ使用不能
こうした状況下で、ラジオは最も信頼できる情報源となります。東日本大震災の被災者調査でも、「役立った情報源」としてラジオが最も高い評価を得ています。
電源確保の課題
災害時の停電は長期化する可能性があります。特に南海トラフ地震では、一部地域で2週間以上の停電が予測されています。そのため、電池に依存しない充電手段を確保することが重要です。
- 手回し充電:いつでも発電可能(無いよりあったほうがマシなレベルで発電効率極悪。)
- ソーラー充電:晴天時に活用可能(一番有望、先のソーラーと蓄電池記事参照)
- 乾電池:長期保存が可能なバックアップ(最悪な状況で使用するようにしましょう)
■防災ラジオの基本機能と選び方
基本機能
防災ラジオを選ぶ際に確認すべき基本機能は以下の通りです:
- 受信バンド:
- AM/FM:基本的な放送受信
- ワイドFM対応:FM補完放送に対応
- 短波/長波:遠距離放送の受信(より広範囲の情報収集)
※一部のAM局は「2028年までにAMを廃止し、FMに一本化してもよい」とされています。
(ただし、災害時の情報発信手段として一部地域では残す方針もあり)
つまり、全国一律に停波ではなく、地域や局の判断によっては残る可能性ありです。
短波は、日本国内向けの短波放送は基本的に終了。
ラジオ電波は周波数が低いほど遠くまで届くという特性があります。
FM(高周波)は音質が良い反面、直進性が強く届く範囲はおおむね数十km。
AM(中周波)は昼でも数十km、夜は数百km〜1000km以上届くことも。
短波(低周波)は電離層反射により、地球規模で通信可能です。
災害時や長距離通信には、周波数の低いAMや短波が有利と言えますが災害大国日本では最低限残しておいても良いんじゃないかと私は思いますね。
- 電源タイプ:
- 手回し充電:停電時に手動で発電
- ソーラーパネル:太陽光で充電
- USB充電:平常時に使用
- 乾電池:バックアップ電源
- 追加機能:
- LEDライト:夜間の照明確保
- サイレン:緊急時の救助要請
- スマホ充電:情報通信手段の確保
- 緊急警報自動受信:自動的に電源が入り警報を受信
選ぶ際のポイント
- 受信感度:建物内でもクリアに受信できるか
- バッテリー容量:どれくらいの時間使用できるか
- 手回し充電効率:1分間の手回しで何分使用できるか
- 防水・防塵性能:屋外や悪天候下でも使用可能か
- 耐久性:落下などに耐えられるか
- サイズと重量:持ち運びやすいか
- 価格:コストパフォーマンス
■防災ラジオおすすめ「Geum016」

📦 必要な機能がこの1台に集約!
「Geum016」は、防災士監修という安心感のもと設計された、非常時に本当に役立つ多機能ラジオです。見た目はコンパクトながら、いざというときに頼れる機能がぎっしり詰まっています。
✅ ラジオ機能(AM/FMワイドFM対応)
- 地域の災害情報や避難指示をキャッチするにはラジオが最も確実。
- Geum016はAM/FMに対応しており、FM補完放送(ワイドFM)も受信可能。
- 音質は明瞭で、小音量でもはっきり聞こえる設計。夜間の避難所などでも◎。
🔋 電源が途絶えても安心の「3WAY電源」
- 手回し発電(ダイナモ)
- ソーラーパネル充電(晴天時に便利)
- USB充電(普段の備えに)
停電中でもラジオ・ライト・スマホ充電ができるのは安心感が段違い。
手回しハンドルはスムーズで軽く、1分程度の回転でまぁまぁ電力が蓄えられます。
📱 スマホの充電も可能(USB出力ポート搭載)
- 緊急時、スマホは「命を守るツール」。
- Geum016はスマホへの簡易充電が可能で、通話や連絡手段を維持できます。
- 完全充電には時間がかかりますが、「数回の通話」や「LINE1往復分」は十分カバー可能。
💡 LEDライト・SOSアラーム・コンパス付き
- 強力LEDライトは夜間の避難・停電時の作業に最適。
- SOSアラーム機能は音+点滅ライトで、遭難時や救助要請に使える。
- IPX3相当の防水加工
✋ 実際に使ってみて感じたこと(使用感レビュー)

- 本体は片手で持てるサイズ感で、リュックにもすっぽり入る。
- ボタンやつまみも大きめで、高齢者や子どもでも操作しやすい設計。
- ラジオ感度も良好で、都市部でもノイズ少なくクリアに受信。
💬 防災用としてだけでなく、「キャンプ・アウトドア」や「日常のラジオ生活」にも使えるデザイン性と機能性があります。
懸念点:Geum016のチューナーはデジタル方式で、選局がしやすいのは魅力ですが、個人的に気になるのは「デジタルが壊れるとチューニングできなくなる」という点。
アナログ式であれば多少の故障でも“音を拾って探る”ことができますが、デジタル式は液晶や基板が故障したら操作不能になります。
普段使いには便利でも、「壊れにくさ・復旧しやすさ」という防災の観点では一考の余地があるポイントです。
Geum016に加え、単3乾電池1~2本で動くアナログチューニングAM/FMラジオを一台用意すると安心です。
稀に海外製の周波数帯が違う、感度が凄く悪い製品などがありますので気をつけましょう。
私のおすすめは、下記2点です。
オーム電機AudioCommポケットラジオAM/FM ワイドFM
gemean超小型ラジオAM/FM ワイドFM
■まとめ:理想的な防災ラジオの選び方
災害時の状況に応じた理想的な防災ラジオの選び方をまとめます。
防災ラジオの効果的な活用方法
- 平常時の準備:
- 定期的に充電し、いつでも使える状態にしておく
- 月1回程度の動作確認を行う
- 乾電池は別途保管し、定期的に新品に交換する
- 家族全員が操作方法を理解しておく
- 主な局の周波数は手書きメモをしてラジオに貼り付けておく
- 災害時の活用法:
- 最初に地域の防災情報を確認(NHKや地域FM局)
- バッテリー消費を抑えるため、情報収集は定時のニュースを中心に
- スマホ充電は緊急連絡用に必要最低限に抑える
- ソーラー充電と手回し充電を状況に応じて使い分ける
- 省エネ活用のコツ:
- ラジオとライトを同時に使用しない
- 必要な時だけ電源を入れる
- 音量は聞こえる最小限に設定
- 晴れている日中はソーラー充電を優先
まとめ
いかがでしたか?防災ラジオは単なる情報収集ツールではなく、照明確保やスマホ充電など多くの機能を持つ重要な防災アイテムです。特に南海トラフ地震のような大規模災害に備え、自分や家族のニーズに合った防災ラジオを選んでおくことをおすすめします。
次回は「LED防災ライト・ランタン」について詳しく解説する予定です。停電時の明かり確保は安全と心理的安定のために非常に重要です。ぜひお楽しみに!
あなたの家庭には防災ラジオがありますか? ぜひコメント欄で教えてください。。