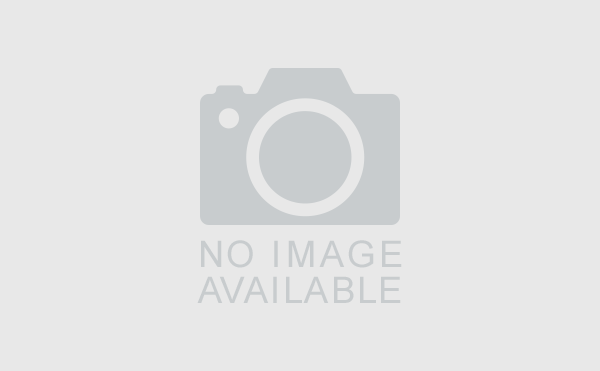【防災シリーズ⑨】防災用調理器具:災害時にも温かい食事を:実践編-後半

前半では各種調理器具🍳の特徴や選び方について解説しました。後半では、**実際の災害時を想定した調理方法**や、**事前の準備**について詳しく見ていきましょう。
📋 目次
1. [災害時の段階別調理計画]
2. [燃料別の調理効率と保存方法]
3. [災害時の水事情と調理時の節水テクニック]
4. [カセットコンロの安全な使用法と応用テクニック]
5. [防災食材と組み合わせた簡単レシピ集]
6. [実践!災害時調理シミュレーション]
7. [まとめ:災害時の調理に備えるための10か条]
🕰️ 災害時の段階別調理計画
🔥災害発生からの時間経過によって、調理環境や食材の状況は変化します。段階に応じた調理計画を立てておくことが重要です。
⚡ 発災直後(〜24時間)

想定される状況:
・ライフラインの寸断(電気・ガス・水道の停止)
・混乱と不安で落ち着いた調理が難しい
・冷蔵庫内の食材はまだ傷んでいない
電線断線による漏電、ガス管破損によるガス漏れには十分に気をつけましょう。
適した調理器具:
✅ カセットコンロ(簡単に点火できるタイプ)
✅ 固形燃料コンロ(安全に使いやすい)
調理のポイント:
・火を使わない、または最小限の加熱で済ませる
・単純な調理方法を選ぶ(お湯を沸かす程度)
・冷蔵庫内の傷みやすい食材から優先的に使用
・水の使用量を最小限に抑える
おすすめメニュ:
1. カップ麺や即席スープ(お湯だけで調理可能)
2. 缶詰をそのまま、または軽く温める
3. 冷蔵庫内の野菜を使った簡単炒め物
🏠 災害発生後2〜3日目

想定される状況:
・ライフラインは依然として復旧せず
・冷蔵庫内の食材は使い切るか傷み始める
・避難所や支援物資の情報が入り始める
適した調理器具:
✅ カセットコンロ(メインの調理に)
✅ 保温調理器(燃料節約のため)
✅ 無水調理鍋(水の節約のため)
保温調理器がなければ、鍋を新聞紙や毛布で包んで代用できます。熱いうちに包み、数時間そのままにしておくことで余熱調理ができます。
調理のポイント:
・燃料と水を節約する工夫を凝らす
・複数の料理を同時に作る効率化
・保存食と組み合わせた調理
・調理器具の洗浄に使う水を最小限に
おすすめメニュー:
1. 乾麺や乾燥野菜を使ったスープ
2. レトルト食品をアレンジした料理
3. 缶詰を使った簡単炊き込みご飯
🌦️ 災害発生後4〜7日目

想定される状況:
・部分的にライフラインが復旧し始める可能性
・備蓄食材が減少してくる
・支援物資や炊き出しなどが本格化
適した調理器具:
✅ 複数の熱源を使い分ける(カセットコンロ、固形燃料、焚き火など)
✅ ソーラークッカー(晴れた日の日中)
✅ 簡易燻製器(食材の保存に)
調理のポイント:
・配給された食材も組み合わせて調理
・長期保存が難しい食材から使う
・複数の世帯で共同調理も検討
・調味料を工夫して単調さを緩和
| 時間帯 | おすすめメニュー | 使用する調理器具 |
|---|---|---|
| 朝食 | 野外炊飯(おかゆ) | 焚き火台 |
| 昼食 | 乾物を戻した具沢山の煮込み料理 | 保温調理器 |
| 夕食 | 保存食をベースにした汁物 | カセットコンロ |
🏙️ 災害発生後1週間以降
想定される状況:
・徐々にライフラインが復旧
・食材の入手ルートが確保され始める
・長期化する場合は避難生活の疲れが出始める
適した調理器具:
✅ 薪ストーブや焚き火台(燃料持続性)
✅ 多機能調理器(バリエーション確保)
✅ DIY調理器具(状況に応じた応用)
長期化する災害では心理的な疲労も考慮して、時には「いつもの味」を再現することも大切です。簡単なアレンジで食事に変化をつけましょう。
調理のポイント:
・燃料の自給自足も視野に入れる
・栄養バランスを意識した献立
・地域でのシェアリングや情報交換
・心理的な安定も考慮した「楽しめる」調理
おすすめメニュー:
1. 季節の野菜を使った具だくさん料理
2. パンやピザなどの焼き物(可能であれば)
3. 保存食と新鮮食材を組み合わせた料理
⛽ 燃料別の調理効率と保存方法

各種燃料の特性を理解し、効率的に使い分けることが長期の災害対応には欠かせません。
🔥 カセットガス
熱効率:
・発熱量:約7,000kcal/缶
・1缶の使用時間:強火で約1.5時間、中火で約2.5時間
・水1リットルを沸騰させるのに要する時間:約4〜5分
✅ 効率的な使用法
- 料理の下準備をしてから点火する
- 鍋は必ず蓋をして熱効率を上げる
- 強火で一気に加熱し、あとは弱火か余熱を利用
- 風防を使って熱の分散を防ぐ
- 複数の料理を同時進行で行う
⚠️ 保存上の注意点
- 高温下での保管は缶の変形や爆発の危険性あり
- 冬場の低温環境では気化が悪くなり火力が低下
- 年に1回程度は古いものから使用して新しい在庫と入れ替える
- 未使用・使用済みのボンベを明確に区別して保管
在庫管理の目安:
・1日3食×家族人数×7日分を基本に計算
・使用量目安:一人一食あたり約10分使用として計算
・例:家族4人で1週間の場合、4人×3食×7日÷6食/缶≒14缶
🧱 固形燃料
種類別熱効率比較:
| 種類 | 燃焼時間 | 発熱量 | 水1Lの沸騰時間 |
|---|---|---|---|
| メタ型(小) | 約20分 | 約400kcal | 約8〜10分 |
| メタ型(大) | 約40分 | 約800kcal | 約6〜8分 |
| ジェル型 | 約120分 | 約1,500kcal | 約7〜9分 |
| パラフィン型 | 約30分 | 約600kcal | 約8〜10分 |

**効率的な使用法**:
1. 風の影響を受けないよう囲いを作る
2. 鍋底と固形燃料の距離を適切に保つ(3〜5cm程度)
3. 複数個使用する場合は等間隔に配置
4. 必要に応じて途中で消火し、再使用する(メタ型の場合)
5. 専用の五徳(鍋置き)を使用して安定させる
固形燃料が尽きた場合、廃油キャンドルを自作することもできます。使用済みの食用油に古いロウソクの残りや綿を混ぜて作る簡易燃料は、緊急時の強い味方になります。
🌳 木質燃料(薪・小枝)
種類別熱効率:
| 燃料 | 発熱量(kg当たり) | 特徴 |
|---|---|---|
| 広葉樹(ナラ・カシなど) | 約4,500kcal | 火持ちが良い、温度が安定 |
| 針葉樹(松・杉など) | 約4,000kcal | 着火しやすい、火力が強い |
| 小枝・落ち葉 | 約3,500kcal | 着火材として最適、短時間燃焼 |
効率的な収集と使用法:
1. 細い枝→中くらいの枝→太い木の順に組み合わせる
2. 乾燥した木材を選ぶ(湿った木は燃えにくく煙が多い)
3. 樹種を混ぜることで着火性と持続性を両立
4. 風向きを考慮した配置と換気
5. 残り火と灰の有効活用(保温や次の着火に)

💧 災害時の水事情と調理時の節水テクニック
災害時には水の確保が最大の課題となります。調理においても水をいかに節約するかがポイントです。
🚰 災害時の水源確保
日常的に備蓄すべき水の量:
・飲料水:1人1日3リットル×最低3日分
・調理用水:1人1日2リットル×最低3日分
・ 合計:1人あたり最低15リットル(2Lペットボトル約8本分)

代替水源の活用法:
🛁 風呂の残り湯
用途:調理器具の洗浄、野菜の洗浄、米のとぎ汁代わり
保存法:浴槽にフタをする、消毒用塩素を少量加える
注意点:飲用には適さない、数日で腐敗する可能性あり
☔ 雨水
用途:調理器具の洗浄、野菜の下洗い
集め方:バケツ、レジャーシート、雨どい
注意点:屋根からの最初の雨水は汚れているため避ける
🏞️ 河川・湧き水
用途:浄水処理後の調理、洗浄
採取法:清流の流れのある場所から採取
注意点:必ず浄水処理(煮沸または浄水剤)を行う
水の浄化方法:
1. 煮沸:
・方法:沸騰後1〜3分間維持
・効果:ほとんどの細菌・ウイルスを死滅させる
・注意点:化学物質は除去できない
2. ろ過:
・方法:布→砂→炭→砂の層を通す
・効果:濁りや不純物を除去
・注意点:微生物の完全除去は難しい
3. 浄水剤・浄水器:
・方法:錠剤を水に溶かす、または専用フィルターでろ過
・効果:細菌・原虫などを除去または不活性化
・おすすめ製品:カタダイン「マイクロピュア」、MSR「ミニワークス」
緊急時の簡易浄水器は、ペットボトルの底を切り、上下逆さにして使うことができます。上から順に、布(コーヒーフィルターなど)→砂→活性炭→砂→小石と層を作り、水を通すことで不純物をある程度除去できます。
🚿 調理時の節水テクニック

調理前の工夫:
1. 計画的に調理して水の使用回数を減らす
2. 汚れやすい調理器具の使用を最小限に
3. 調理器具に油を薄く塗っておくと洗いやすい
4. 食材の下ごしらえを最小限にする
調理中の工夫:
1. 無水調理法:
・野菜自体の水分を利用
・少量の油で蒸し焼きにする
・密閉性の高い鍋を使用する
2. 一鍋調理法:
・複数の食材を一つの鍋で調理
・順番に入れることで別々の食感に
・洗い物の数を減らせる
3. 蒸し調理の活用:
・少量の水で複数の食材を調理可能
・栄養素の流出も最小限
・簡易蒸し器:鍋の中に皿を置き、その上に食材を置く
洗浄時の工夫:
1. 使う前に新聞紙や食品ラップを敷いておく
2. 油汚れは使用済みのティッシュなどで拭き取ってから洗う
3. 米のとぎ汁や茹で汁を洗浄に再利用
4. 最後にすすぐ水は次の調理器具の一次洗浄に使う
5. 食器を「拭き取り洗い」で済ませる
- 朝食:インスタントオートミールに少量の熱湯を注ぐ(使用水量:約100ml)
- 昼食:乾パンと缶詰(水不要)
- 夕食:
- 無水鍋で缶詰の具材と乾燥野菜を炒める
- 少量の水(約300ml)で戻しながら煮込む
- 残りの煮汁でカップ麺を作る
- 洗浄:残りの約600mlで全ての調理器具を段階的に洗浄
🔋 カセットコンロの安全な使用法と応用テクニック
カセットコンロは災害時の主力調理器具ですが、正しく使わないと危険です。安全な使用法と効率的な活用法を解説します。

🛡️ 安全な使用環境と注意点
使用場所の選定:
水平で安定した場所に設置
周囲に燃えやすいものがない場所
風の影響を受けにくい場所
換気の良い場所(一酸化炭素中毒防止)
子どもやペットが近づかない場所
使用前の確認事項:
1. コンロ本体に破損や変形がないか
2. ボンベの接続部に問題がないか
3. 点火装置が正常に作動するか
4. 周囲の安全確認(可燃物の有無など)
5. 消火器や水の準備
カセットコンロによる火災事故の主な原因は、「ボンベの過熱」と「不適切な場所での使用」です。使用中はボンベが熱くなっていないか定期的に確認し、換気の良い場所で使用しましょう。
使用中の注意点:
1. 調理中はその場を離れない
2. 使用時間は連続1時間以内を目安に(過熱防止)
3. 天ぷらなど油を大量に使う調理は避ける
4. 鍋からはみ出す大きな食材を調理しない
5. ボンベが熱くなりすぎていないか定期的に確認
使用後の手順:
1. 完全に消火したことを確認
2. ボンベを取り外して保管(特に気温の高い日)
3. 本体が冷えてから収納
4. 五徳や周辺の清掃
5. 次回使用に備えた点検
トラブル対応:
🔍 火がつかない場合
- 点火装置の確認
- ボンベの残量チェック
- 接続部の清掃
- マッチやライターでの代替点火
🔊 異常な炎や音がする場合
- 即座に使用中止
- ボンベを安全に取り外す
- 風防の位置調整
- 異物混入の確認
💨 ガス漏れの疑いがある場合
- すぐに火気使用中止
- 窓を開けて換気
- ボンベを取り外す
- 石けん水で漏れ箇所を特定
📊 効率的な調理テクニック
熱効率を高める工夫:

1. 風防の活用:
・市販の専用風防
・アルミホイルで簡易風防
・鍋の周りに石や煉瓦を配置
2. 適切な鍋の選択:
・平底で火の大きさに合った鍋
・熱伝導率の高い素材(アルミ、銅など)
・蓋の密閉性が高いもの
3. 熱反射板の使用:
・アルミホイルを敷いて反射させる
・断熱材の上に設置
・空き缶で作る簡易反射板
燃料節約の調理法:
1. 予熱と余熱の活用:
・火にかける前に室温に戻しておく
・沸騰後すぐに火を止め、余熱で調理
・保温容器やアルミホイルで包んで余熱調理
2. 圧力調理の応用:
・圧力鍋があれば調理時間を1/3に短縮
・代替品:密閉性の高い鍋+重石
・水の沸点を上げて調理効率アップ
3. 下ごしらえの工夫:
・食材を小さく切り、調理時間短縮
・乾物は事前に水で戻しておく
・硬い食材は前日から漬け置きする
カセットコンロの炎は鍋底の中心に集中させるのが効率的です。鍋底全体に炎が広がるように調整すると、実は熱の無駄遣いになります。中心部に集中した強い炎のほうが、熱効率が良くなります。
カセットコンロの応用活用法:
1. オーブン代わりに:
・大きな鍋の中に小さな容器を置く
・鍋に少量の水を入れ、蓋をして蒸し焼きに
・アルミホイルで包んで焼く
2. トースター代わりに:
・網や鉄板をコンロの上に置く
・パンの両面を軽く焼く
・フライパンに蓋をして焼く方法も
3. 燻製器として:
・二重鍋を用意(下に水、中に燻製チップ、上に食材)
・弱火でじっくり加熱
・アルミホイルで煙が漏れないよう密閉
🍲 防災食材と組み合わせた簡単レシピ集

災害時でも栄養バランスを考えた食事を摂ることが大切です。備蓄食材を活用した簡単レシピを紹介します。
🥫 缶詰活用レシピ
ツナ缶ドライカレー ⭐⭐⭐⭐☆
材料:ツナ缶1缶、乾燥玉ねぎ大さじ2、カレー粉小さじ2、ご飯1合分
調理法:
1. カセットコンロでフライパンを温め、ツナ缶(油ごと)を入れる
2. 乾燥玉ねぎを加えて軽く炒める
3. カレー粉を加えて香りが出るまで炒める
4. ご飯を加えて全体を混ぜ、水分がなくなるまで炒める
– 調理時間**:約10分
– 燃料消費**:カセットコンロ 約10分(1/15缶程度)
さば缶トマトパスタ ⭐⭐⭐⭐⭐
材料:さば水煮缶1缶、トマト缶1/2缶、乾燥パスタ100g、乾燥パセリ少々
調理法:
1. 鍋にお湯を沸かしてパスタを茹でる(表示時間の8割程度)
2. 別のフライパンにさば缶を汁ごと入れ、トマト缶を加える
3. 茹で上がったパスタの湯を少量取り置き、パスタをさば缶のソースに絡める
4. 乾燥パセリを振りかける
– 調理時間:約15分
– 燃料消費:カセットコンロ 約15分(1/10缶程度)
さば缶は良質なタンパク質とオメガ3脂肪酸が豊富。トマト缶と組み合わせることでリコピンも摂取でき、免疫力維持に役立ちます。災害時の体調管理に最適な組み合わせです。
コーンビーフ簡易ハッシュドポテト ⭐⭐⭐☆☆
材料:コーンビーフ缶1缶、乾燥マッシュポテト1/2カップ、お湯1/2カップ
調理法:
1. 乾燥マッシュポテトをお湯で戻す
2. フライパンにコーンビーフを広げて中火で炒める
3. 香ばしくなったらマッシュポテトを加えて混ぜ合わせる
4. 平たく広げて両面を焼く
– 調理時間:約10分
– 燃料消費:カセットコンロ 約10分(1/15缶程度)
🍚 乾物活用レシピ
切り干し大根のトマトスープ ⭐⭐⭐⭐☆
材料**:切り干し大根30g、トマトジュース缶1缶、コンソメ顆粒1袋
調理法**:
1. 切り干し大根を軽くすすぎ、食べやすい長さに切る
2. 鍋にトマトジュースと水1/2カップを入れて火にかける
3. 切り干し大根とコンソメを加えて10分程度煮込む
4. 大根が柔らかくなったら完成
– 調理時間**:約15分
– 燃料消費**:カセットコンロ 約15分(1/10缶程度)
高野豆腐のカレー煮 ⭐⭐⭐⭐☆
材料:高野豆腐2枚、カレールウ1かけ、乾燥野菜ミックス大さじ2
調理法:
1. 高野豆腐をぬるま湯で20分程度戻し、食べやすい大きさに切る
2. 鍋に水1カップと乾燥野菜を入れて火にかける
3. 野菜が戻ったら高野豆腐を加え、カレールウを溶かす
4. とろみがついたら完成
– 調理時間**:約20分(戻し時間除く)
– 燃料消費**:カセットコンロ 約10分(1/15缶程度)
高野豆腐は災害時の強い味方です。乾燥状態で長期保存でき、戻すと約5倍に膨らみます。良質なタンパク質源として、様々な料理に活用できます。戻す際に少量の塩を加えると、より早く戻ります。
乾麺de焼きそば ⭐⭐⭐☆☆
材料:インスタント焼きそば1袋、乾燥キャベツ大さじ2、魚肉ソーセージ1本
調理法:
1. 乾燥キャベツを少量の水で戻しておく
2. 鍋に水を入れて乾麺を規定時間より1分短く茹でる
3. フライパンに茹でた麺、戻したキャベツ、細切りにした魚肉ソーセージを入れて炒める
4. 付属のソースをかけて混ぜ合わせる
– 調理時間**:約15分
– 燃料消費**:カセットコンロ 約15分(1/10缶程度)
🍛 レトルト食品アレンジレシピ
カレーリゾット ⭐⭐⭐⭐⭐
材料:レトルトカレー1袋、アルファ米1袋
調理法:
1. アルファ米に規定量の水を加えて戻す
2. 戻したご飯の半量をボウルに取り出す
3. レトルトカレーを温め、ご飯に混ぜ合わせる
4. 好みで温めた水を加えて濃度を調整する
– 調理時間:約10分(米の戻し時間除く)
– 燃料消費:カセットコンロ 約5分(1/30缶程度)
ハヤシライス風リメイク ⭐⭐⭐⭐☆
材料:レトルトシチュー1袋、ケチャップ大さじ1、アルファ米1袋
調理法:
1. アルファ米を規定の方法で戻す
2. レトルトシチューを温め、ケチャップを混ぜる
3. 温かいご飯にかけて完成
– 調理時間**:約10分(米の戻し時間除く)
– 燃料消費**:カセットコンロ 約5分(1/30缶程度)
パスタソースdeスープ ⭐⭐⭐☆☆
材料:レトルトパスタソース1袋、乾燥スープの素1袋、水200ml
調理法:
1. 鍋に水を入れて温め、スープの素を溶かす
2. レトルトパスタソースを加えて混ぜる
3. 沸騰直前で火を止め、蓋をして数分蒸らす
– 調理時間:約10分
– 燃料消費:カセットコンロ 約8分(1/18缶程度)
📋 レシピカードをダウンロードできます 📋
上記レシピをまとめたPDF形式のレシピカードを作成しました。
印刷して防災バッグに入れておくと、いざというときに便利です。
🎮 実践!災害時調理シミュレーション

実際の災害時を想定したシミュレーションを行い、事前の備えと練習の重要性を確認しましょう。
📅 電気・ガス・水道が止まった状況での1日の食事プラン
想定条件
家族4人(大人2人、子ども2人)
夏の暑い日(食材の傷みやすい状況)
電気・ガス・水道が完全に停止
備蓄食材と調理器具のみで対応
準備している調理器具
カセットコンロ(1台)とボンベ(予備含め4本)
固形燃料コンロと燃料(10個)
保温調理器(シャトルシェフ)
多機能クッカー(鍋、フライパン兼用)
ケトル
断熱効果のあるクーラーボックス
⏰ タイムスケジュール
| 時間 | 作業内容 | 使用器具 |
|---|---|---|
| 7:00 | 朝食準備開始 | カセットコンロ |
| 7:30 | 朝食 | – |
| 12:00 | 昼食準備開始 | 固形燃料コンロ |
| 12:30 | 昼食 | – |
| 17:00 | 夕食準備開始 | カセットコンロ、保温調理器 |
| 19:00 | 夕食 | – |
朝食(7:00〜8:00):
メニュー:アルファ米と缶詰の具材、インスタントみそ汁
使用器具**:カセットコンロ、ケトル
手順:
1. カセットコンロでケトルのお湯を沸かす(約300ml)
2. アルファ米に熱湯を注いで5分待つ
3. 残りの熱湯でインスタントみそ汁を作る
4. 缶詰(ツナや鯖)を開けてご飯にのせる
– 注意点:
– 食器は使い捨て紙皿を活用して洗い物を減らす
– 残った缶詰は傷まないよう涼しい場所で保管
– 使用した熱湯は冷めてから拭き掃除に使用
昼食(12:00〜13:00):
メニュー:カップ麺とレトルトおかず
使用器具:固形燃料コンロ、小型鍋
手順:
1. 固形燃料コンロに火をつけ、小型鍋で水を沸かす(約600ml)
2. カップ麺に熱湯を注ぎ、3分待つ
3. レトルト食品をお湯に入れて温める(湯せん)
4. 残ったお湯は冷まして保存(後で使用)
– 注意点:
– 固形燃料の消費を抑えるため、一度に必要な分だけお湯を沸かす
– 日陰で食事し、こまめに水分補給する
– 使い捨て箸やスプーンを活用

夕食(18:00〜19:00):
-メニュー:無水調理de野菜と缶詰の煮込み、乾パン
使用器具:カセットコンロ、保温調理器(シャトルシェフ)
手順:
1. 多機能クッカーに缶詰(肉や魚)を汁ごと入れる
2. 乾燥野菜や残っている生野菜を加える
3. 調味料で味付けし、10分程度強火で煮る
4. 沸騰したら火を止め、保温調理器に入れて2時間ほど置く
5. 保温調理器から取り出し、必要に応じて再加熱して食べる
– 注意点:
– 残った調理物は夜間の気温を考慮して保存方法を工夫
– 調理器具の洗浄は最小限の水で(拭き取り→すすぎ)
– 保温調理器の活用で燃料を大幅に節約
💧 1日の水使用量
- 飲料水:4人×2L = 8L
- 調理用水:約2L
- 洗浄用水:約2L
- 合計:約12L
⛽ 1日の燃料使用量
- カセットコンロ:約20分(1/7缶程度)
- 固形燃料:2個(約40分相当)
省エネ効果:保温調理器の活用で約60分の燃料節約
🔄 1週間シミュレーションの重要ポイント
実際の災害時には、1週間以上のライフライン停止も想定されます。長期対応のポイントを確認しましょう。
食材のローテーション:
1. 傷みやすい食材から使用
・冷蔵庫内の生鮮食品(24時間以内)
・冷凍食品(解凍後24時間以内に使用)
・開封済みの食品
2. 次に使用する食材
・缶詰・レトルト食品
・乾物(乾麺、乾燥野菜など)
3. 長期保存用食材は後半で
・アルファ米・乾パン
・フリーズドライ食品
・栄養補助食品

燃料の計画的使用:
| 期間 | 使用する燃料 | 温かい食事の回数 | 工夫ポイント |
|---|---|---|---|
| 初期 (1〜2日目) |
カセットコンロをメインに使用 | 1日3回 | 冷蔵庫内の食材を優先的に使用 |
| 中期 (3〜5日目) |
固形燃料と併用 | 1日2回 | 保温調理を積極的に活用 |
| 後期 (6日目以降) |
燃料を最小限に抑える | 1日1回 | 代替熱源(日光、車のエンジン熱など)も活用 |
栄養バランスの確保:
🥩 タンパク質源
- 缶詰の魚・肉
- 高野豆腐
- 乾燥大豆
- 魚肉ソーセージ
🥬 ビタミン・ミネラル源
- 乾燥野菜
- 乾燥果物
- 缶詰野菜・果物
- 海藻類
🍚 炭水化物源
- アルファ米
- 乾麺
- 乾パン
- クラッカー
🥜 脂質源
- ナッツ類
- 缶詰の油
- 小袋調味料の油
- チョコレート
実践トレーニングの提案:
・年に2回(夏と冬)の防災食シミュレーションを実施
・実際に電気・ガスを使わない1日体験を家族で行う
・備蓄食材の調理実習を定期的に行い、味や作り方を確認
・子どもも参加できる簡単な調理方法を練習しておく
📝 災害時調理チェックリスト
以下のチェックリストを印刷して、定期的に確認しましょう。
カセットボンベの残量と使用期限確認
固形燃料の残量と使用期限確認
保温調理器の状態確認
調理器具の清潔さと保管状態確認
家族全員が使用方法を理解しているか確認
備蓄食材の状態と使用期限確認
水の備蓄量確認
使い捨て食器の備蓄確認
レシピカードの保管場所確認
📝 まとめ:災害時の調理に備えるための10か条

災害時の調理に備えるための重要ポイントを10か条にまとめました。これらを意識して準備しておくことで、いざというときの不安を軽減できます。
1️⃣ 複数の熱源を確保する
カセットコンロだけでなく、固形燃料や薪ストーブなど異なるタイプの調理器具を備える。火起こし道具(ライター、マッチ、火打石など)も複数準備。
2️⃣ 燃料の備蓄は最低7日分
カセットボンベは家族人数×2本/日×7日分を目安に。固形燃料は家族人数×3個/日×7日分。定期的にチェックし、ローリングストックで常に新鮮な状態を維持。
3️⃣ 節水調理を意識した器具選び
無水調理鍋や保温調理器を優先的に備える。調理と洗浄の両方で水の使用量を減らせる工夫を。
4️⃣ 実際に使える調理器具を選ぶ
普段から使い慣れておくことが重要。家族全員が操作できる簡単な仕組みのものを。収納しやすく、持ち出しやすいサイズ感。
5️⃣ 備蓄食材と調理法をセットで考える
食材だけでなく、その調理方法まで想定しておく。実際に試作して確認し、必要な調味料も備蓄。レシピカードを作成して非常用バッグに入れておく。
6️⃣ 多機能性を重視する
一つの器具で複数の調理ができるものを選ぶ。調理以外の用途(暖房、湯沸かし、消毒など)も考慮。部品の互換性があるとなお良い。
7️⃣ 安全性を最優先に
屋内使用可能かどうかを確認。子どもがいる家庭は特に安全装置付きのものを。消火器や耐熱手袋なども併せて準備。
8️⃣ 定期的なメンテナンスを忘れずに
半年に一度は点検と試用を行う。部品の破損や劣化がないか確認。燃料の使用期限と保管状態をチェック。
9️⃣ 省エネ調理のコツを習得する
保温調理や無水調理の方法を家族で練習。一度の加熱で複数の調理を行う効率化を学ぶ。夏と冬で異なる調理法を想定しておく。
🔟 地域の状況も考慮した準備を
住んでいる地域の災害リスクに応じた対策。マンションと一戸建てで異なる制約への対応。避難所生活も想定した携帯性の高い調理セットも。
💭 最後に
災害はいつ起こるか分かりません。しかし、適切な準備と知識があれば、その不安を大きく軽減できます。特に「食」は生命維持だけでなく、精神的な支えにもなります。日頃から防災意識を高め、家族で防災食の試食会や調理練習を行うことをおすすめします。
いざというとき、温かい食事が作れることは、想像以上に大きな安心につながります。この記事が皆さんの防災準備の一助となれば幸いです。